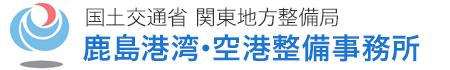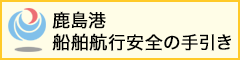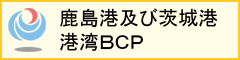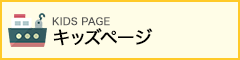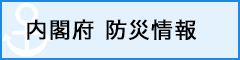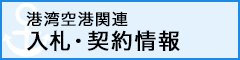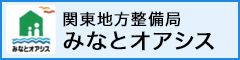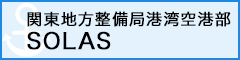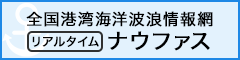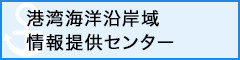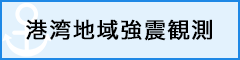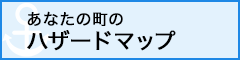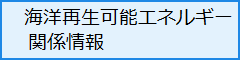茨城港(日立港区)の概要

内貿貨物とともに外貿貨物の取扱いが進展する「茨城港日立港区」
昭和32年に新たに埠頭の建設が着手されて以来、42年には重要港湾の指定を受け発展を続けてきました。港内には整備中の第3ふ頭を含めると5つのふ頭があります。
現在は、完成自動車輸出入の一大拠点として、また北関東への燃料供給基地として活況を呈しています。
なお、第5ふ頭においては、国内最大規模のLNGタンクを有する「日立LNG基地」が平成28年3月より稼働を開始しました。
日立港区開発の経緯
日立港区は整備前まで、隣接する久慈漁港の副港としての役割を持つ漁港でした。
一方、本港の背後地は、大規模な工場地帯、原子力関係産業地域を抱えており、全国屈指の工業地でしたが、昭和30年代の高度成長期生産規模の拡大、搬出物品の大型化とともに近隣に港湾施設不足していることから、港湾整備の要請の高まりを受けて、昭和32年に整備が開始されました。
太平洋の激流や、久慈川河口の流下土砂対策等、多くの課題を克服しつつ施設の整備が行われ、港勢は急速に進展し、昭和42年6月には重要港湾の指定を受けました。
現在、常磐自動車道の関東の玄関口という地の利を生かし、首都圏へのバラ貨物輸送拠点、完成自動車の輸出入基地として発展しています。

昭和31年撮影

昭和57年撮影

令和元年撮影
沿革
| 1957(昭和32)年 | 5月 | 第1埠頭着工 |
|---|---|---|
| 1959(昭和34)年 | 10月 | 第1船入港 |
| 1960(昭和35)年 | 7月 | 第1埠頭3,000t岸壁完成 |
| 1962(昭和37)年 | 12月 | 港湾運送事業法に基づく指定港になる |
| 1965(昭和40)年 | 第2埠頭着工 | |
| 1967(昭和42)年 | 6月 | 重要港湾に指定される 関税法に基づく開港となる |
| 11月 | 第2埠頭10,000t岸壁完成 | |
| 1973(昭和48)年 | 10月 | 検疫法に基づく指定港になる |
| 1976(昭和51)年 | 11月 | 第5埠頭着工 |
| 1981(昭和56)年 | 4月 | 第2埠頭供用開始 |
| 11月 | 第5埠頭供用開始 | |
| 1984(昭和59)年 | 2月 | 九州定期コンテナ航路開設(2006年6月航路廃止) |
| 1985(昭和60)年 | 5月 | 四国定期コンテナ航路開設(2007年4月常陸那珂港へシフト) |
| 1986(昭和61)年 | 2月 | 東南アジア定期コンテナ航路開設(2005年5月航路廃止) |
| 1989(平成元)年 | 6月 | 第4埠頭-12m岸壁供用開始 |
| 1990(平成2)年 | 7月 | 日立港物流センター完成 |
| 1991(平成3)年 | 12月 | 第4埠頭 コンテナターミナル供用開始 |
| 1992(平成4)年 | 1月 | メルセデス・ベンツ日本 日立市に新車整備センターを稼働 |
| 7月 | 物流センターに冷凍倉庫が完成、第2埠頭に県営3号上屋(燻蒸倉庫)が完成 | |
| 1993(平成5)年 | 7月 | 釧路港との定期RORO航路開設 |
| 1997(平成9)年 | 6月 | 釧路とのRORO船サービスデイリー化 |
| 1998(平成10)年 | 4月 | 第5埠頭-12m岸壁供用開始 |
| 1999(平成11)年 | 3月 | 港湾計画改訂 |
| 2006(平成18)年 | 6月 | 北九州定期RORO航路開設(2011年2月常陸那珂港区へシフト) |
| 2008(平成20)年 | 12月 | 県北3港統合により茨城港誕生 |
| 2009(平成21)年 | 3月 | 港湾計画改訂 |
| 2010(平成22)年 | 4月 | メルセデス・ベンツ日本の新車整備センターが日立市に統合 |
| 5月 | 日産自動車による北米向け乗用車の輸出が開始 | |
| 2011(平成23)年 | 3月 | 東日本大震災発生 |
| 12月 | 港湾計画一部変更 | |
| 2012(平成24)年 | 7月 | 日立LNG基地着工 |
| 12月 | 第3埠頭地区着工 | |
| 2014(平成26)年 | 7月 | 西欧定期RORO航路開設 |
| 2015(平成27)年 | 3月 | 港湾計画一部変更 |
| 2016(平成28)年 | 3月 | 日立LNG基地稼働 |
| 2018(平成30)年 | 3月 | 第3ふ頭-12m岸壁供用開始 |
茨城港(日立港区)の主な立地企業