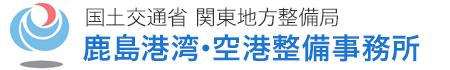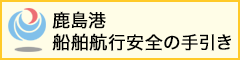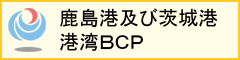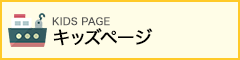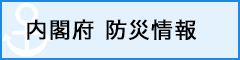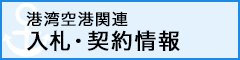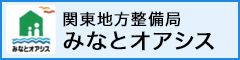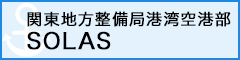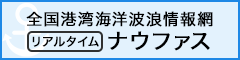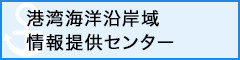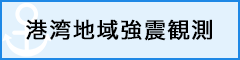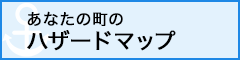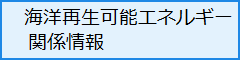用語辞典
あ
アプローチ航路
外海から泊地に向かって行く部分の航路。
アンカー
海上に浮かんでいる船を固定するのに使う碇。
浮桟橋
箱型の浮く形状のもので造ったさんばしで、潮の満ち引きの差の大きいところに設けられ、ポンツーン(pontoon)と呼称される。
上屋(うわや)
荷揚げした貨物や船に積み込む貨物の荷さばき(処理)や、一時保管のために利用する建物。保管を目的とする倉庫とは異なる。
越波(えっぱ)
波の力によって、海水が防波堤や岸壁などの構造物の上の面(天端)を超えること。
エプロン(apron)
岸壁の海側の隅の角部から上屋の壁前面までの岸壁の表面。
追い波
船を追いかける方向から進んでくる波。反対は向かい波。
大潮
新月または満月の二、三日後に起こる潮差の最も大きな潮。
親潮
千島列島沿いから三陸沖に南下する寒流。
か
ガントリークレーン
コンテナ埠頭に設置される貨物の積み卸しを行うためのクレーン。
きっ水
船体の水面下に沈んでる深さ。
くずれ波
波の峯が白く泡立ち始め、それがだんだん波の前面に広がっていく波。
黒潮
日本の太平洋沿岸を北上する暖流。
ケーソン
主として鉄筋コンクリートでつくった箱状または円筒状の構造物。
コンテナ(container)
もとは「容器」のこと。貨物を合理的に輸送するために開発された輸送容器のこと、アルミ製が主。サイズは長さを表し、10(約3メートル)・20(約6メートル)・40(約12メートル)フィートが主流で、最近は40フィートが多い。
コンテナターミナル
コンテナを取り扱う施設。
さ
最大波
群の中で一番大きな波のこと。正確にはある統計期間内の最大の有義波(波高の大きい方から数えて1/3の数の波高と周期を平均したもの)。
砂質ローム
軟弱な土質を改良するためにサンドパイル(軟弱地盤に入れる砂の柱)を打ち込む船。
シーバース
主としてタンカーのためにある海上での船舶の停泊場所。
消波ブロック
波力をなくすことを目的に造られたコンクリートブロック。
SOLAS条約 Safety of Life at Sea
1974年の海上における人命の安全のための国際条約。
た
耐震強化岸壁(耐震バース)
大規模な地震が発生した場合に、被災直後の緊急物資及び避難者の海上輸送を確保するために、特定の港湾において、通常のものより耐震性を強化して建設される岸壁をいう。
高潮
強風や気圧の急変などのために潮位が上昇すること。
潮差
高潮と低潮との海面の差。
津波
海底地震が起こり、それに伴う海底の上下運動によって発生した波。
テクノスーパーテクノライナー(TSL)
速力50ノット(時速約93km)、貨物積載重量1000トン、航続距離500海里(約930km)以上、波浪階級6程度の荒れた海でも安全に航行でき、耐航性に優れいることを目標に開発した超高速船。
ドライドッグ
船舶の建造修理やコンクリートケーソンの製造に使われる排水可能なドッグ。
トランスファークレーン
コンテナヤードでコンテナを積み重ねたり積み下ろしをする橋型のクレーン。
は
バース(berth)
船を係留する場所。
泊地
船が安全に停泊するための水域。
波高
波の峯と谷との高さの差。
波長
波の峯から次の峯までの水平距離。
波浪
風浪とうねりを合わせた呼び方。
ピア(pier)
さん橋
プッシャー
押し船。はしけ(本船と波止場の間を往復して乗客や貨物を運ぶ小船)などを船首で推し進める船。
防玄(舷)材
船の舷側(両側面)が接触して衝撃を防ぐために取り付けられているもの。
防潮堤
海水が陸へ侵入するのを防ぐための堤防や護岸。
ま
巻き波
波の峯が前方へ投げ出され、巻き込むように砕ける波。
水先案内
船が港や航路を航行するとき、船長に代わり、また助けて船を安全に誘導すること。
や
矢板
地中に打ち込む板状の杭。鋼製・木製・コンクリート製がある。
養浜
海岸に砂を補給したり、突堤を築いて砂が溜まって海岸を造成すること。
ら
乱積み
捨て石やブロックなどの投げ込みのまま積み上げること。順序よく積むことは「正積み」。
リアス式海岸
多数のおぼれ谷(地上部分だった谷が土地の沈下によって海中に没した地形)のある海岸。日本では三陸海岸が有名。
陸棚
大陸または島の周辺の水深200メートルまでの傾斜のゆるやかな海底部分。